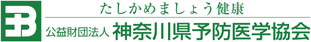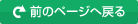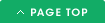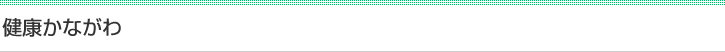
欧米の挑戦
「がん死亡率が減少」。驚くべきニュースが九〇年代初頭、米国を駆けめぐった。六〇年代後半のニクソン大統領以来、三十年にわたって「対がん戦争」をスローガンに、喫煙率の低下や食生活の改善に、国を挙げて取り組んできた成果が初めて数字にあらわれた瞬間だった。国民の「健康志向」を喚起した作戦は功を奏し、ジョギングやダイエットブームまで巻き起こした。中でも、最も効果があったのが喫煙率の低下だった。たばこを吸っている人は、吸わない人の数倍から数十倍がんになる率が高い。そこで、レストラン、オフィスなど、人が集まる場所は全面的に禁煙化。喫煙率は少しずつ減少し、その十年二十年後、後を追うようにがん死亡率も減少に転じた。
また、ヨーロッパでも予防への取り組みが功を奏し、フランス、イギリスなどでがん死亡率を減少させることに成功している。
これに対し、日本では戦後、一貫してがん死亡率は上昇の一途をたどっている。がんによる死者は、年間二十八万人。欧米では、予防によりがんが減り始めたというのに、わが国の取り組みは遅々として進まず、逆に若年層を中心に喫煙率が増加するなど、「認識不足」の感は否めない。
「新幹線事故で毎日、一本の列車の乗客全員が亡くなっている計算。しかし、それを深刻に受け止める向きは少ない」。国立がんセンターの杉村隆名誉総長はそう憤る。
「二十一世紀はがん予防の時代」。高齢化に伴い、がんはますます増加傾向になることが予想される。出遅れを巻き返すためにも、いかに効果的な予防策を打ち出すことができるか関心が集まっている。
最先端研究の中で活発なのが、ここ数十年来の遺伝子研究の成果を生かした再発や転移の予防だ。がんにならない一次予防、早期発見の二次予防に対し、この分野は、三次予防と位置づけられている。
人間の遺伝子は、放射線や紫外線などで毎日のように傷ついている。傷が浅ければ修復できるが、機能を保てないほど傷が深ければ細胞は自動的に死んでしまう。しかし、本来の機能を保てないのに増え続ける細胞もある。それが「がん細胞」だ。
三次予防に取り組む東大医科学研究所ヒトゲノム解析センターの中村祐輔教授は、「三年以内には、がんの進行の速さや転移しやすさ、薬の効きやすさなどを、事前に患者ごとに診断できる"オーダーメード医療"の基盤が確立するはず」と予言する。
遺伝子を調べる技術の向上は著しく、今年のがん学会では一万個以上の遺伝子を一度に調べる新手法が大々的に紹介された。この手法を用いれば、がん患者と健康人、抗がん剤が効いた人と効かずに死亡した人の遺伝子などを比較することがようにになる。どの遺伝子の働きに違いがあるのか解析し、診断、治療に役立てることも容易だ。
中村教授らも、最近、この技術を使って抗がん剤の効きやすさに関係する新しい遺伝子十個を発見、その一部を今年の学会に報告した。
こうした成果を利用して、がんの悪性度の診断や、転移予防薬、副作用の少ない抗がん剤開発などに応用できる日はそう遠くない。
がんはもはや「不治の病」ではなくなってきている。二十年前に比べて五年生存率は大幅にアップしており、早期発見して適切に治療すれば完治することも多くなってきた。早期発見率を上げるためにも、がん検診の精度向上と充実が期待されるところだが、厚生省の「がん検診の有効性評価に関する研究班」(総括班長・久道茂東北大教授)が昨年春、これまでの検診の有効性に疑問を呈して以来、そのあり方が論議を呼んでいる。
報告書によると、肺がん、乳がん検診は「効果はあっても小さい」という。これに対し、今年のがん学会で、藤村重文東北大教授らが反論。肺がん検診について、全国五地域での追跡調査の結果を示し、「検診はやはり有効だった」と報告。評価は依然定まっていない。
そんな中、厚生省は昨年、報告書の内容を受け、がん検診の結果を国に報告する必要はないと結論づけた。このため、がん検診のデータが市町村でばらつき、果たして検診は有効なのかどうか決着をつけることがますます難しくなった。
ただ、肺がんでは、国立がんセンターが高性能のコンピューター断層撮影(CT)を検診に導入。早期発見率を高めることで、五年生存率が向上したとの成果を、やはり今年のがん学会で公表した。報告書をまとめた久道教授も「新技術の導入で、有効性の評価が変わってくることはありうる」と指摘する。五年生存率を向上させるためにも、早期発見、治療を可能にする"有効"な検診方法を模索していく努力が求められている。
一次予防対策としては、がんの原因の15%を占めるとされる感染症対策が着々と成果を上げつつある。
年間約三万二千人が死亡する肝がんは、病因の95%がB、C型肝炎ウイルスとされる。しかし感染対策が普及した現在、若年層の肝炎患者が激減。彼らが"がん年齢"に達する三十年後には、三分の一―五分の一まで減少すると言われている。また、胃がんとの関係が疑われるピロリ菌についても、除菌によって胃炎を抑える効果が確認され、来年にも薬による除菌治療が保険適用される見通しとなった。
一方、予防薬の研究も進んでいる。埼玉がんセンターは、緑茶から取り出された「カテキン」などがネズミの大腸がん発生を抑えることを突き止めた。予防薬の研究は欧米でも盛んだ。国内ではまだ予防薬自体が「薬」として認められていないが、米国ではすでに乳がん予防薬タモキシフェンが販売され、話題を呼んでいる。
ただ、感染症対策はすでにゴールが見え始め、予防薬の有効性はまだまだ未知の段階だ。国内のがん患者を減らすためには、それと並行して生活習慣の改善に取り組むことが最も必要だろう。
「たばこを吸わず、酒はほどほど、塩分控えめ、野菜を多く食べる」。国立がんセンターが一九七八年にまとめた「がんを防ぐための十二か条」だ。同省が九〇年から始めた、数万人規模の追跡調査の中間集計が今秋まとまり、この十二か条に当てはまっている人は「がんになりにくい」という客観的なデータも出始めた。
欧米では、生活習慣改善に取り組んでから効果が出るまでに、十―二十年かかった。今、真剣に改善に取り組めば、二十年後にはがん人口が一割減少するという予測もある。富永祐民愛知県がんセンター研究所長は、「日本ではこの期間を少しでも短縮することが欠かせない。地道な取り組みこそ、がんを減らす近道だ」と訴えている。