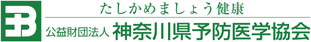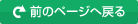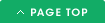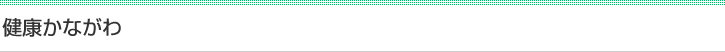
今年の夏、アテネ五輪での日本人選手の活躍に多くの国民がテレビの前で胸を躍らせた。37個のメダルは、わが国の五輪史上で最多。金メダルを獲得した水泳やマラソン、柔道など、感動のシーンは今でも脳裏に焼き付いている。どうして日本はこんなに活躍できたのだろう? さまざまな理由がある。選手が、勝利への強い意思を持ち続けたことが最大の要因だが、選手をバックアップしたスポーツ医・科学の存在も見逃せない。金メダリストを支える「科学技術の力」とは。(読売新聞東京本社科学部次長・佐藤良明)
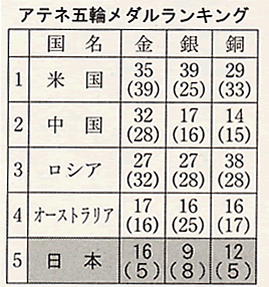 アテネ五輪での日本人選手の活躍をおさらいすると、獲得した金メダル16個、銀9個、銅12個。2000年のシドニー五輪では金が5、銀は8、銅が5だったから大躍進だ。
アテネ五輪での日本人選手の活躍をおさらいすると、獲得した金メダル16個、銀9個、銅12個。2000年のシドニー五輪では金が5、銀は8、銅が5だったから大躍進だ。
日本オリンピック委員会(JOC)は、国のスポーツ振興基本計画を受けて、2001年にゴールドプランと呼ばれる国際競技力向上戦略を発表し、世界のスポーツ列強との戦いに備えてきた。そのプランの中でも、重点施策のひとつとして「スポーツ医・科学の推進」が挙げられている。
ゴールドプランで指摘しているように、米国、フランス、オーストラリアなどスポーツ先進国では自国のトップレベルの選手に対するスポーツ医・科学のサポートが手厚い。
日本でもスポーツ医・科学が本格的に推進されるようになったのは、これら先進国の五輪での躍進が背景にある。グローバル・スタンダードを日本も取り入れる機運になってきたのだ。
アテネ五輪の金メダリストで、スポーツ医・科学による支援を受けた典型的な例が、競泳の男子百メートル、二百メートル平泳ぎを制した北島康介選手だ。
北島選手には国立スポーツ科学センター(JISS、東京都北区)の研究員などサポートスタッフがいて、映像分析、肉体改造など「科学」を味方にして強化を進めた。彼らは「チーム北島」の異名で、知られる存在になった。 サポートでまず挙げられるのはレース分析。日本選手権などの大会で泳ぎを撮影し、飛び込みから15メートルまでの各種データをはじめ、その後の10メートルごとのタイムや、ひとかき、ひと蹴りで進んだ距離、平均スピードなどの「検討材料」を集めた。水中映像から、泳ぎをコンピューターでグラフ化した速度曲線図と呼ばれるデータも点検し、泳ぎのどこに無駄があったのかを科学的に究明していた。
北島選手は世界の一流選手と比べてスタートに改善の余地があり、データをもとに、最初の勝負と言われる「飛び込みから15メートルまで」のタイム短縮に力を注いだ。
次に挙げられるのは、高地トレーニングの活用だろう。
酸素の薄い高地では血液中のヘモグロビンが増え、身体の酸素運搬能力を高める。これまではマラソンに代表されるように持久力の求められる競技で有効とされたトレーニングだったが、短距離の北島選手は別の観点から「高地」に挑戦した。
短距離で使う筋肉は速筋と呼ばれる。これは糖をエネルギーにして動くため、速筋を使えば「疲労物質」である乳酸が身体にどんどんたまる。平地と同じようには身体が動かせず乳酸が出にくくなると一般に言われる高地でのトレーニングは、厳しいメニューを組むことで、平地で経験できないほどの乳酸を身体にため込み、乳酸への耐性を高める試みだった。
北島選手は米国・フラッグスタッフ(標高約二千百メートル)やスペイン・グラナダ(標高約二千三百メートル)などに年間を通じて何度も遠征した。その際にはJISSの研究員が同行し、乳酸や心拍数など生理的データを収集したり、コンディションをチェックするなどして、トレーニングの効果が泳ぎに反映するようサポートしていた。
JISSの川原貴スポーツ医学研究部長は「北島選手ら競泳陣の五輪での好成績は、高地トレーニングの効果をうまく引き出したのが一因」と指摘する。
一方、肉体改造も課題だった。シドニー五輪出場時の北島選手は、高校生だったということもあるが、アテネ五輪時に比べれば明らかに「ほっそり」していた。シドニー以後、専門家の指導を仰ぎながらウエイトトレーニングを行い、「筋量アップ」に励んだ。見た目が立派な筋肉でも、泳ぎに生かせなくては意味がなく、肩関節を滑らかに動かす広背筋や大円筋など様々な筋肉が総合的に力を発揮できるような鍛錬を繰り返した。
女子マラソンで頂点を極めた野口みずき選手もスポーツ医・科学のサポートを受けた。
マラソンは、選手間の駆け引きが見る者をひきつけるが、レース展開以外に、勝敗を左右する要因として、コースが平坦か否か、路面の状況はどうか、など様々考えられる。そうした条件により強化策も変わってくる。
野口選手に対する医・科学サポートでまず挙げられるのは、筋力強化だろう。
アテネのマラソンコースは、標高が最も高い約31キロ地点までは緩急さまざまなアップダウンが断続的に続き、その後、ゴールまでの約11キロは下りだった。長いアップダウンを乗り切るには筋力が必要との判断だった。
長距離ではウエイトトレーニングが軽視されがちだったが、野口選手は積極的に取り入れた。また、野口選手は歩幅の大きいストライド走法だが、この走法も筋力アップにより維持できていたのだ。
一方、野口選手の所属するグローバリーによれば、京都の選手寮には、高地にいるのと同じ環境を再現した低酸素室があり、野口選手はそこで寝泊まりしていた。
空気中の酸素は通常約20%。低酸素室は17%から13%台まで下げることができる。14%を下回ると標高三千から三千五百メートルにいるのと同じ。ふだんの寝起きにも「テクノロジー」を持ち込んで絶えず努力している。ちなみに、この低酸素宿泊室はJISSにもあり、ここをトレーニング拠点としていた北島選手も活用していた。
トレーニング法だけではない。選手が身につける用品にも細心の工夫がある。野口選手のシューズを一例としよう。 提供元のアシックスによれば、開発担当者がアテネのマラソンコースを実際に下見し、路面が大理石の混ざったアスファルトで硬く滑りやすいことを確認した。
選手との情報交換では、着地時にふくらはぎや膝、腰などに衝撃がかかりやすく、体力を消耗しやすいこともわかった。そこで、硬い路面を考慮して、靴底にはクッション性の高いスポンジに籾殻(もみがら)を配合した。また、編み目が大きく汗を吸収しやすいメッシュ素材を上側に使用。汗を素早く吸い取り発散させることで、シューズ内の温度を低く保ち、着地時の衝撃熱でマメができない工夫もほどこした。
医・科学やテクノロジーを結集した末の「栄冠」。スポーツを今までとは違う視点で捉え、新たな興味もわいてくる。 こうした世界のトップレベルの選手とは次元が違うものの、私たちもスポーツを楽しみたい。健康維持に適度なスポーツは有効だ。信州大学大学院加齢適応医科学系の能勢博教授(スポーツ医学)は「こうした地道な医科学のサポート活動と選手の活躍が、ひいては国民のスポーツに対する関心を呼び起こし、国民の健康作りにつながっていくのではないだろうか」と話している。